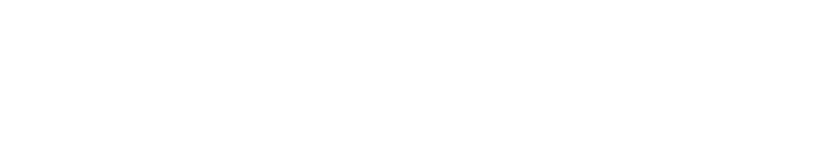特殊な環境の中でも、
最善の医療を尽くす
ようこそ愛知医科大学病院 救命救急科・高度救命救急センターのHPへ。当センターは、1996年に愛知県で最初、国内で8番目に高度救命救急センターの認可を受け、ドクターヘリ運営も20年の実績を誇る施設です。また医学部災害医療研究センターの運営にも携わっており、基幹災害拠点病院として愛知県地域防災計画上重要な役割を担っています。また2023年からは愛知県初の重症外傷センター試行施設に指定され、ショック症状を伴う重症外傷患者さんの集約化を進めて日夜診療能力の向上にも努めています。このHPに訪れて頂いた皆さん、ぜひ私たちの同志として救急災害医療に頑張って行きませんか?
当センターでは、「Academic Critical Care」をモットーに、研究・教育・臨床の3本柱を集結して救急患者全例救命を目指しています。救急現場に医療スタッフが赴き、病院前から早期に治療を開始するドクターヘリ、救急蘇生室ではHybrid ER(重症救急患者の救命に必要な緊急処置が1カ所でできる治療室)の導入も決定しており、それらを最大限に駆使した早期治療介入によるさらなる救命率向上を目指します。そして、救急現場から集中治療室(ICU)管理までシームレスな診療を行います。その個々の患者さんへの診断、治療が、良い転帰に繋がることを励みに取り組んでいますが、それにはPrecision Medicineの概念を背景としたBench to Bedsideの研究と、その活用も欠かせません。このように、研究成果を臨床に生かし、病院前、ERからICU診療まで、全ては目の前の患者救命のために、全職種でmultidisciplinaryなAcademic Critical CareをOne Teamで実践して行く所存です。折しも2023年4月より、私たちが担当する医学部救急集中治療医学講座が設置され、研究・教育に一層士気も高まってきています。ぜひ私たちの現場をのぞいてみてください。
教授渡邉 栄三
Eizo Watanabe
教室の沿革
当院が愛知県第1号、国内8番目に高度救命救急センターの指定を受けたのは1996年です。その後、救命救急科は、2001年6月に設置され、翌2002年に愛知県ドクターヘリ基地局の指定を受けました。すなわち、愛知県で最初に高度救命救急センターの指定を受けると共にドクターヘリ基地病院として地域医療ネットワーク機能を担い、“全患者救命”をモットーに全力で診療に取り組んでおります。また大学附属の教室としての使命を果たすため、他施設では救命出来ない重症患者救命を可能にする高度医療、臨床の疑問点を分子レベルで探求するハイレベルな研究、きめ細かい教育指導による多数の救急医輩出を目標に、日々の業務を実践しています。2023年4月からは医学部「救急集中治療医学講座」として講座化されました。昨今のCOVID-19パンデミックにより、集中治療への社会的認知度は高まり、日本専門医機構サブシャリティ領域に集中治療科が認定されました。今後も救急集中治療医学講座開設を契機として、地域における救急集中治療・災害医療の充実化、基礎から臨床医学に渡る侵襲学領域の研究・医学教育のさらなる発展に貢献する所存です。
歴代教授
麻酔学講座と兼任
教室員9名~16名、非常勤医師1名~3名
教室員11名~16名、非常勤医師3名~5名
教室員13名~20名、非常勤医師8名~10名
教室員14名(救急診療部2名を除く)、非常勤医師 8名~10名(令和5年5月現在)
救命救急センターの指定を受ける。ICU6床が救命救急センター内に整備される。
ICU6床に加えHCU20床が増床される
ICU8床、HCU20床に増床される
ICU10床、HCU20床に増床される
重症熱傷治療ユニット2床をICUに包括
高度救命救急センターの指定を受ける(国内8番目)
愛知県ドクターヘリ基地局の指定を受ける(国内4番目)
基幹災害拠点病院指定
新病院EICU12床、HCU20床
ER部門の臨床、教育、研究を推進する目的で救急診療部が設置され、救命救急科の加納秀記教授(特任)が初代教授に就任した
新型コロナ患者対応陰圧室整備EICU6床(12床中)、HCU20床(20床中)、ER
愛知県重症外傷センター試行施設に指定(県内2施設)
愛知医科大学医学部に救急集中治療医学講座が開設され、救命救急科の渡邉栄三教授が初代教授に就任した